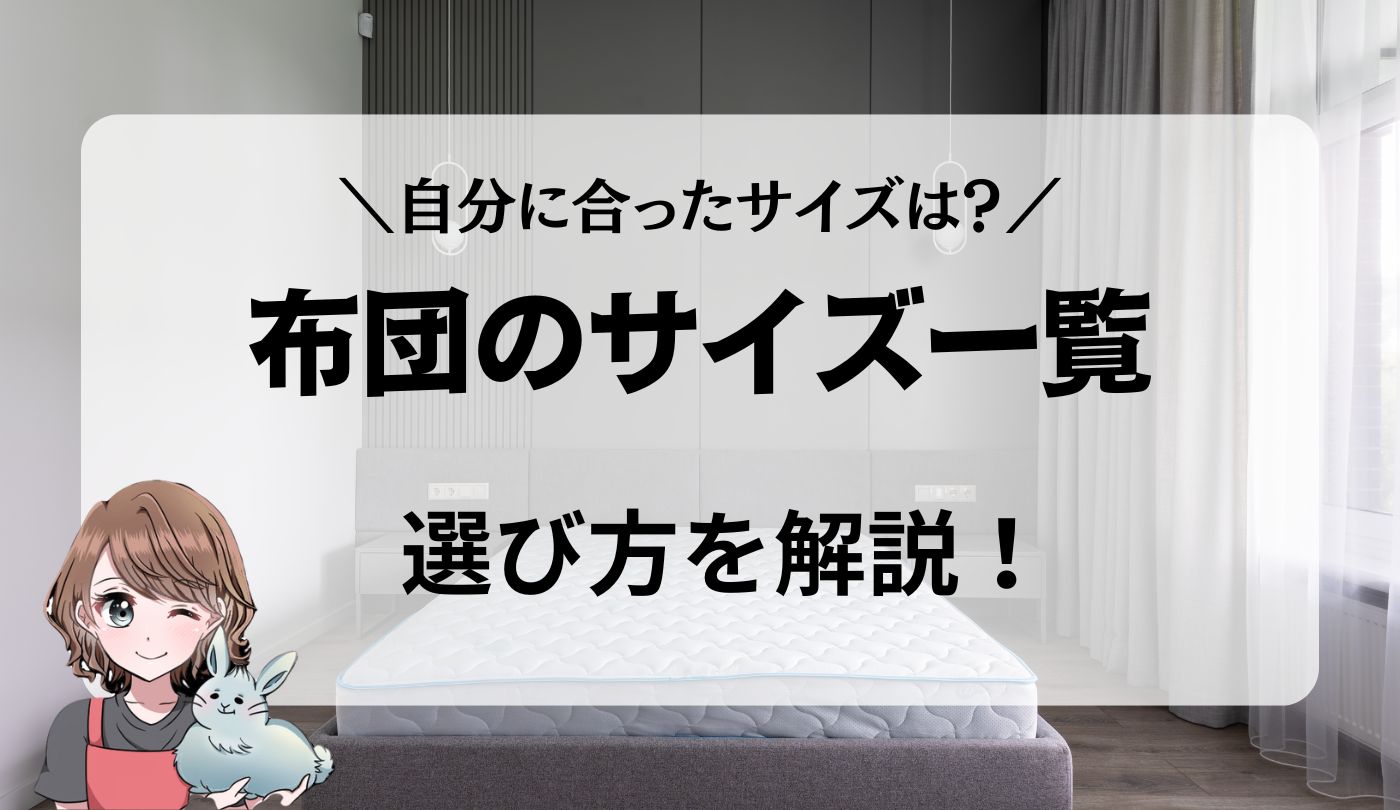布団を買い替えを検討しているから、サイズについて知っておきたい!

敷布団とマットレスでは、大きさが違うって本当?
毎日使う「布団」ですが、サイズについては理解できていないという方も多いのではないでしょうか?
一言で「布団」といっても、サイズや種類はさまざまです。
自分の体型やライフスタイルに合った布団サイズを把握しておくと、朝の目覚めが良くなったり睡眠の質が上昇したりするメリットも。
また、布団を買い替える際にも、スムーズに選ぶことができるので安心です。
そこで本記事では、布団のサイズ一覧や敷布団とマットレスのサイズ表記の違い、快眠できる布団の選び方について詳しく解説していきます。
布団サイズはもちろん、自分に合った布団の選び方を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてくださいね!
布団のサイズ一覧
一言で「布団」といっても、そのサイズはさまざまです。
また、敷布団と掛け布団でも大きさは違ってきます。
布団のサイズを知っておくことで、新しい寝具を購入する際にもスムーズになるでしょう。
たくさんの種類があるので、すべてを覚えておくのは難しいかもしれません。購入する可能性のあるサイズだけでもチェックしておくと安心ですね。
【布団のサイズ一覧表】
| 布団の種類 | 敷布団(幅×丈) | 掛け布団(幅×丈) |
|---|---|---|
| ベビーサイズ | 90cm×130cm | 110cm×130cm |
| キッズサイズ | 90cm×160cm | 120cm×160cm |
| ジュニアサイズ | 90cm×185cm | 135cm×185cm |
| シングル | 100cm×200cm | 150cm×210cm |
| セミダブル | 120cm×200cm | 170cm×210cm |
| ダブル | 140cm×200cm | 190cm×210cm |
| クイーン | 160cm×200cm | 210cm×210cm |
| キング | 180cm×200cm | 230cm×210cm |
| シングルロング | 100cm×210cm | 150cm×230cm |
| ダブルロング | 140cm×210cm | 190cm×230cm |
上記が、一般的な「敷布団」「掛け布団」のサイズとなります。
ただし、商品や販売されているメーカーによって、若干サイズが異なるケースもあるため注意しなければなりません。
また、ベッド用の敷布団サイズは上記でも触れたように「丈:200cm」というのが基本です。
一方「直置き用」の敷布団の場合は、丈の長さが「210cm」になることを覚えておきましょう。
近年、セミダブルサイズの布団の販売数は減少傾向にあります。また、クイーンサイズやキングサイズに関しても「受注生産」となる可能性がありますので注意してくださいね!
敷布団とマットレスのサイズ表記の違いとは?
敷布団とマットレスは、共に「就寝時に敷く布団」という役割があります。
しかし、この2つには表記や用途の違いがあるため、注意が必要です。
- マットレスは「幅」「丈」の他に「厚み(高さ)」の表記がある
- 敷布団とマットレスではサイズが違う
- マットレスは大きく分けて3種類ある
敷布団との1つ目の違いは、マットレスには「厚み(高さ)」の表記がある点です。
もちろん、敷布団にも厚みはありますが「幅×丈」の表記しかありません。
一方マットレスには、必ず「厚み(高さ)」の表記があるので確認してみましょう。

確かに、床に直接マットレスを敷くときには、厚みがポイントになりそうね。
薄いマットレスだと、底つき感があったり耐久性にも不安があったりするかもしれません。湿気もこもりやすくなるので、慎重に選んでくださいね。
2つ目の違いは、サイズです。
例えば、シングルサイズのマットレスの場合「95cm×195cm」のものが一般的。上記でも解説したように、敷布団のシングルサイズは「100cm×200cm」ですので、幅も丈も異なります。
シーツなどを購入する場合には、マットレスのサイズを把握しておくことが大切です。
敷布団とマットレスの違い3つ目は、マットレスは大きく分けて3つの種類に分けられること。主に「ベッド用マットレス」「低反発マットレス」「高反発マットレス」の3つです。
ベッド用マットレスは、ベッドフレームの上に置いて使用するタイプ。十分な厚みがあり、通気性や耐久性に優れているものが多くなっています。
低反発マットレスは、反発弾性率が15%未満のマットレスのこと。反発する力が小さいため、身体を包み込むような寝心地が特徴です。身体の凹凸にもピッタリとフィット!体圧分散にも非常に優れています。
ただし、通気性はあまりよくありません。また、低反発マットレスの素材はウレタンフォームが多いため、水洗いできない点がデメリットと言えるでしょう。
高反発マットレスは、寝返りのしやすさが魅力のマットレス。身体が深く沈みこまないため、腰痛持ちの方にも最適です。
通気性と耐久性に優れているのもポイントのひとつ。
デメリットは、保温性が低いため肌寒く感じてしまう可能性もある点や、低反発マットレスと比べて高額な商品が多いことが挙げられるでしょう。
快眠できる布団の選び方
布団を選ぶ際には、どのような点に注意すれば良いのでしょうか?
人生の3分の1は睡眠時間です。睡眠の質が向上すれば、必然的に日々のパフォーマンスも上がり、疲労回復にもつながります。
「快眠」「安眠」できる布団の選び方を知って、健康的な毎日を過ごしたいものです。
- サイズで選ぶ
- 掛け布団は重さと保温性がポイント
- 敷布団は通気性と硬さをチェック

それぞれ詳しく知りたいわ!
ここからは、3つのポイントに分けて解説していきます。
これから布団を購入する方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
布団のサイズで選ぶ
布団を選ぶ際のポイント1つ目は、やはり「布団のサイズ」です。
まずは、自分に適したサイズの布団を把握しなければなりません。
敷布団のサイズは「幅:肩幅+30cm」「丈:身長+35cm」が必要だと言われています。
これは最低限のサイズです。そのため、これ以上大きくても、全く問題ありません。
ただし、大きいサイズを購入する場合は「部屋の間取りや大きさ」にも注意が必要です。
大きすぎる布団は、生活スペースがなくなってしまうこともありますし、最悪の場合「布団が敷けない」という可能性も。
自分の身体に見合ったサイズを選ぶことはもちろん、部屋の大きさも考慮して選ぶようにしましょう。
掛け布団は重さと保温性がポイント
掛け布団の選び方は「重さ」と「保温性」が重要です。
掛け布団は、ある程度の重みがなければ眠れないという人も少なくありません。
しかし、あまりにも重たい掛け布団を選んでしまうと、身体を圧迫したり寝返りも打ちにくくなったりします。
適度な重さを意識して、フィット感のあるものを選ぶのがポイント。
また、保温性も重視しなければなりません。

確かにそうね。
布団の中がひんやりしていたら、なかなか寝付けないわ。
保温性の高い掛け布団は、睡眠中も快適な温度を保ってくれます。
羽毛布団は保温性にも優れており、心地良い肌触りで安心して眠れるでしょう。
敷布団は通気性と硬さをチェック
敷布団を選ぶときには、通気性と硬さのチェックが大切です。
人は眠っているときに「コップ1杯分」の汗をかくといわれています。
これは、どれだけ機能性に優れた布団を選んでも、避けることのできません。
毎日使う敷布団は、寝汗によってカビが発生する恐れも。
通気性の良い素材を選ぶのがおすすめです。
また、敷布団は人それぞれ「好みの硬さ」がありますよね。
硬さを選ぶ際には「寝姿勢」や「腰痛持ちかどうか」などで決めることができます。
仰向けで寝る人は「硬め」の敷布団がおすすめ。横向き寝の人は、柔らかめを選ぶと良いでしょう。
腰痛持ちの方が「柔らかめ」の敷布団を選ぶと、症状が悪化するケースもあります。腰に痛みがあるときは、硬めの敷布団(マットレス)を選びましょう。
体型によって硬さを決めるのも一つの方法です。
身体が小さかったり体重が軽かったりする方には「柔らかめ」の敷布団、一方身体が大きく、体重が重い場合には「硬めの敷布団」を選ぶのがおすすめです。
まとめ|布団を購入する際は事前にサイズをチェックしよう
本記事では、布団のサイズ一覧や敷布団とマットレスのサイズの違い、快眠できる布団の選び方について詳しく解説してきました。
布団のサイズを事前に把握しておくと、購入するときにも迷わずにすみます。
自分の身体の状態や寝姿勢・部屋の大きさなど、さまざまな観点から最適な布団を選ぶようにしましょう。
睡眠時間は、人生の3分の1を占めていますので、布団選びは慎重に行うようにしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。以上、参考になると幸いです。